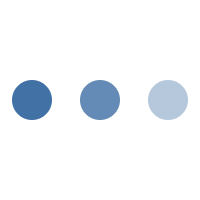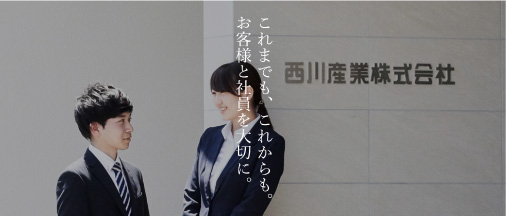太陽光発電2
投稿日:2025.04.09
2009年以前のソーラーシステムは、家庭用の自家消費がメインでした。
太陽光で発電した電力を家庭内で消費し、余った分を電力会社が買い取りました。
買取価格は、一般家庭の標準の電気料金1kWh24円と同じです。(売りと買いが同じ)
目安として、10年で初期投資を回収し、残り10年は無料の電気が使えるというのがキャッチフレーズでした。
4人家族の家庭ですと、4kWのソーラーを屋根に付ければ、年間を通じて電気代が差し引きゼロになる計算です。
ZEH(「ゼッチ」)はゼロエネルギーハウスの略ですが、ソーラー無しには語れません。
2012年にFIT制度が始まり業界の様子が少し変わってきました。
発電した電力を20年間に渡って、全量を買い取る制度で、スタート直後は1kWh40円でした。
家庭用の電気代が、1kWh24円ですから、破格の高額ということになります。
40円と24円の差額は、割賦金と言って、国民が電気代の一部として負担することが決まりました。(国は何も支出しない)
このFIT制度は、2004年にドイツで始まり欧州で普及していました。
しかし、1kWh80円という価格設定により、割賦金の高さに国民から不満の声が上がり、2012年に廃止されました。
日本でも、導入を検討していましたが、反対する声がでていました。しかし、
2011年に東北大震災が起きて、原発が停止、再生可能エネルギーが電源として注目され、2012年にFITが導入されました。
この高買取価格に目を付けた事業者が、次々と参入し、ゴルフ場跡地などにソーラー発電所を建設して行きました。
国は、買取価格を毎年下げて行きましたが、数が増えると部材価格が下がり、業者のメリットがあり、増加し続けました。
「発電事業者の利益」 = 「20年間の売電収入」 ー 「初期投資と維持費用」
20年間の買取期間中、6年程で初期投資を回収し、14年は電気を売って儲ける商売が流行しました。
2015年くらいから、大きな問題もでてきました。
・発電した電力を送る送電線が足りない。(メガソーラーの乱立)
・原発が再稼働すると、電気が余ってくるので、買取ができなくなる。
・再エネ割賦金が、どんどん上がって、家庭の負担になってきた。(現在、月1600円近くを負担、知っていました?)
買取価格が1kW15円を下回った2019年からは、新たにFITを申請する事業者は殆どなくなりました。
ただし、2012年に申請し、施工されずに残っている計画が、昨年度までは、実行に移されるケースがありました。
(当初、国のミスで施工期限を決めていなかった。途中でルールを変更し期限を決めた。民主党政権の時代で、詰めが甘い。)
2025年度は買取価格が1kWh9円、もうソーラーで儲けようと考える事業者は居なくなるでしょう。
ところが、同じ再エネでも、洋上風力発電は買取価格が1kWh36円なのです。
海上なので建設費が高く付くという理由付けはありますが、業界関係者と政治家の癒着が噂されています。(犠牲になるのは国民)
良くCO2削減の為に再エネ推進が必要だと言われますが、ソーラーメーカーの志は、最初から自産自消を目指しています。
結果として、火力発電の量が減って、CO2削減に貢献はしますが、「電気を買わない生活」というのが究極の目標です。
日本の工場は、世界で最も省エネが進んでいると言いますが、屋根にソーラーを付けて自産自消も進めるべきでしょう。
最近は、PPAモデル(Power Purchase Agreement )と言って、
PPA業者が、工場の屋根や空き地を無償で借りて、ソーラーの設置とメンテナンスを行い、工場はその電力を安く買う。
というビジネスモデルが流行しています。初期費用無しでソーラーを導入できるメリットがあります。
関西電力もこの事業に参入しており、工場やオフィスは安い電力が使え、関電は休日の余った電気を利用しています。
おわり
![]()
営業本部 エンジニアリンググループ
山本 一詞
新着記事
-
2026.02.06
-
2026.01.16
-
2026.01.06
-
2025.12.19
-
2025.12.16
-
2025.12.02
-
2025.11.17
-
2025.11.04
-
2025.10.16
-
2025.10.02